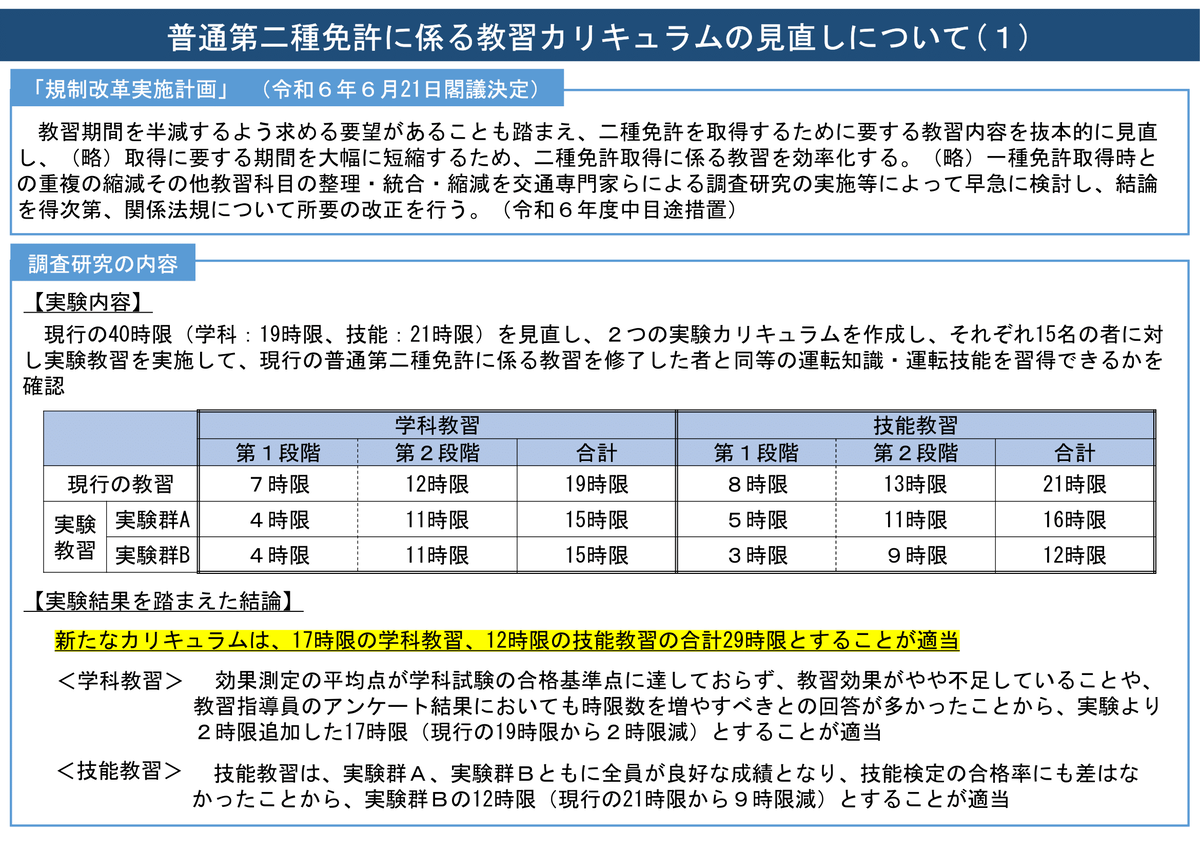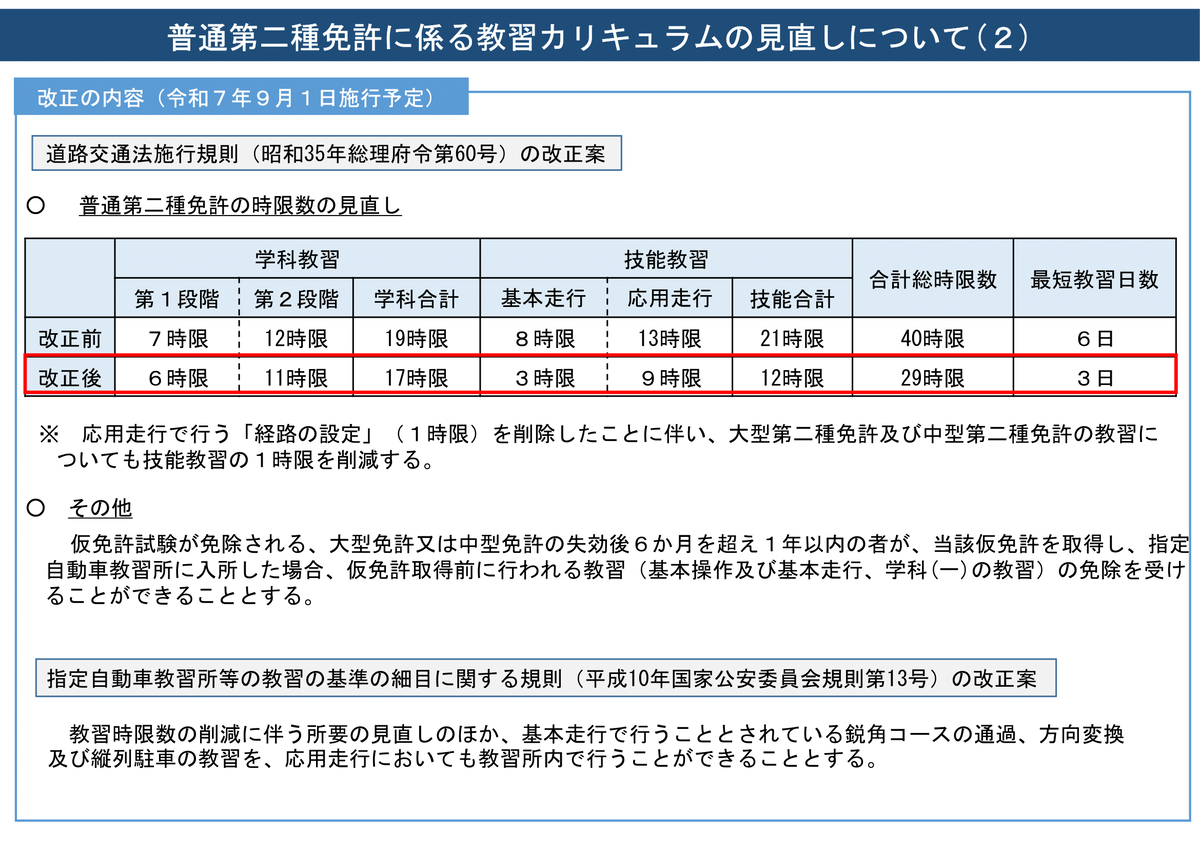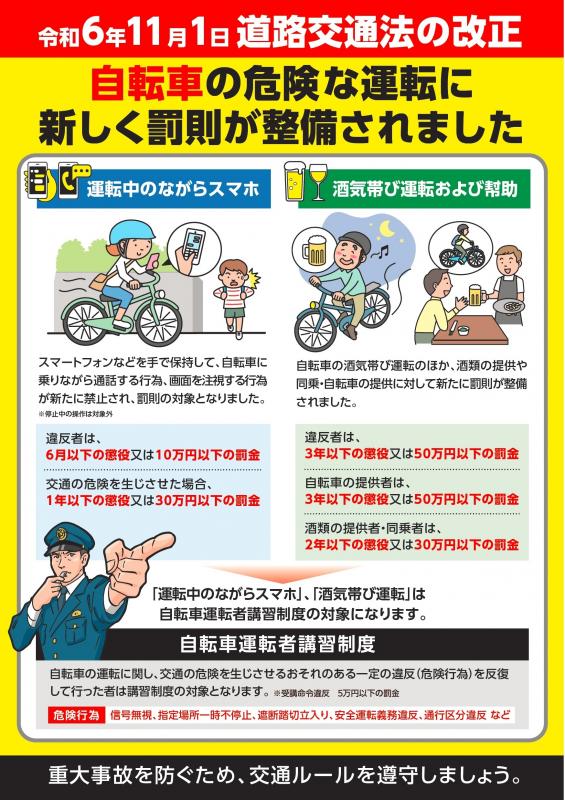高速道路の料金所はこんな感じ! 画像:写真AC
皆さんこんにちは!(^^)!
今回の内容は、前回の続き「高速道路での運転」後半になります。
前回は「故障時などの措置」までお話しましたので今回は「高速道路利用上の心得」からお話していきますね。
それでは早速行ってみましょう!
高速道路利用上の心得
高速走行中はちょっとした準備不足が大きな危険につながります。もちろん体調管理も大切ですし、時間や自動車の管理も大切ですよね。
前もって自動車の点検をして、無理のない運転計画等の準備も行いましょう。
車の点検
高速道路では燃料、冷却水、エンジンオイルの不足による走行困難がないように、特につぎの点検をしなければなりません。
①燃料の量は十分か
②冷却水の量が規定の範囲内にあるか
③ラジエータキャップが確実に閉まっているか
④エンジンオイルの量が適当であるか
⑤ファンベルトの張り具合が適当であるか、また損傷がないか
⑥タイヤの空気圧は適当であるか(高速走行するときは、やや高めにする)
⑦タイヤの溝の深さが十分か
積荷の点検
積荷が転落・飛散しないようにしっかり点検し、必要ならば積み直しなどを行わなければなりません。
停止標示機材の用意
高速道路でやむを得ず停止するときは、停止標示器材を置かなければなりません。
前もって車に積んでおきましょう。
走行計画の立てかた
無理のない運転計画
2時間に1回くらいの間隔で休憩できるような運転プランを立てましょう。
疲れを感じたときはプランと違っても休憩を取るようにしましょう。
体調を整える
高速では速い速度で走行をしながら正確な情報収集と的確な状況判断、操作が求められるため、ミスしないためにも体調を整えておくことが大切です。
本線車道への進入
高速道路への入りかた
標識などによる確認
高速道路へ向かうときは一般道路にある緑色の案内標識をよく確かめ、インターチェンジ(一般道路と高速道路を接続する場所)の入口を間違えないようにしましょう。
ゲートへの入りかた
高速道路のゲート(料金所)では、早めにどのブース(通行券を受け取ったり、料金を支払ったりする場所)に入るか決めるようにしましょう。ETC付きの車でETCを利用する場合はETCレーンへ、それ以外の方は一般のレーンに入りましょう。
通行券や料金の受け渡し
ブースでは、通行券などの受け渡しをしやすい位置に必ず停止します。
無人ブースの場合、ブースから離れすぎた場所で停止すると通行券が取れないこともあるので注意が必要です。
本線車道への進入
目的地の確認とランプウェイの走行
ゲート通過後は行き先を案内標識でよく確かめ、進入方向を間違えないように進みます。間違えた場合、戻ることはせずに次のインターチェンジまで行って引き返しましょう。
加速車線の活用
本線車道に入るときは加速車線を使ってしっかりと加速して、他の車と速度を合わせたうえで入るようにしましょう。
本線車道の車の妨害禁止
本線車道に進入するときは、本線車道を通行する車の進行を妨げないようにしましょう。また、本線車道と本線車道が合流するところで表示により優先が指定されいるときは、それに従いましょう。
本線車道での走行

高速道路のトンネスは要注意 画像:写真AC
急ブレーキの回避
高速走行中に急ブレーキを掛ければスリップの原因になってしまいます。
早めに状況を判断し、アクセルを緩めたり、1段低いギアに落としてエンジンブレーキを使うとともに、ブレーキは数回に分けて掛けるようにしましょう。
特に二輪車の場合は、転倒のおそれが高いのでより注意しましょう。
急ハンドルの回避
高速走行中の急ハンドルは車の安定性を失い、横転やスリップにつながりやすいです。早めに状況をとらえて少ないハンドル操作で避けられるようにしましょう。
トンネル進入時の減速
トンネル進入時には目が慣れる(暗順応)まで時間がかかり、視力が低下した状態になります。そのためトンネル前ではあらかじめスピードを落とし走行しましょう。
インターチェンジなどの付近を走行するとき
他の車が加速車線から合流してくることを考え、速度を落としたり、追い越し車線に移って進路をゆずってあげましょう。
疲労時の措置
高速運転は緊張の連続から疲労しやすいです。疲れや眠気を感じたらサービスエリアやパーキングエリアに車を止めて、仮眠や体操をするなどして、疲れを取りましょう。
追い越し
追い越しは交通事故の可能性が高まります。不必要な追い越しや危険を感じる追い越しはやめましょう。追い越す場合は前後の車や進路、速度に注意して行いましょう。
天候などに応じた運転
雨天時などの運転
雨天時に高速走行するとスリップしたりハイドロプレーニング現象(水膜現象)が発生するおそれがあります。また、雪の日は滑りやすく視界も悪いため速度を落とし、車間距離をいつも以上に取らなければなりません。
強風時の運転
強風のときはハンドルを取られ、ふらついたり、はみ出したりしやすくなるので注意が必要です。特にトンネルの出口などで横風にあおられやすいので気をつけなければなりません。
夜間の運転
夜間は視界が悪く落下物への反応が遅れたり、前車との距離感を見間違えたりしやすくなります。速度を控えめにし、心にゆとりを持てるように走行しましょう。
本線車道からの離脱
案内標識によるインターチェンジと出口の確認
本線車道から離脱するときは、あらかじめ、案内標識をよく見て出口を行き過ぎないように気をつけましょう。出口の案内標識は2km、1km、500m手前にあります。
出口が近づいてきたときは追い越しは控えましょう。
減速車線の活用
離脱するときは減速車線に早めに入り、減速車線で減速するようにしましょう。本線車道で著しく減速してしまうと後続車に追突されるおそれがあります。
ランプウェイ走行時の注意
ランプウェイ(高速道路と一般道などの2つ以上の道路が交差又は接近する箇所において、これらの道路を立体的に接続させている連結道)はカーブや坂が続くので、十分に速度を落として走行しましょう。
出口ゲート付近での注意
ゲート付近では、速度感覚のくるいなどから追突事故が発生することがあります。早めに十分速度を落とすようにしましょう。また、どのレーンに行くかも早めに決めましょう。
一般道路に応じた速度
高速道路から一般道路に出たときは、速度感覚がくるっているので速度メーターを頻繁に見たり、一度休息を取ってから走行するようにしましょう。
まとめ
今回は学科教習の最後となる「高速道路での運転」についてでした。
ここまで一緒に勉強してくれた皆さんは路上を運転するために必要な知識が身についたことと思います。
ただ、もちろん1回ではなく、何回も読み返してもらえたら幸いです。
安全な交通社会は誰かが作ってくれるものではなく一人一人の運転者が自分にできることして、その結果として出来上がっていくものです。そのことを忘れないでくださいね!
新潟県公安委員会指定 水原自動車学校
フリーダイヤル:0120-62-0808
公式ホームページ:https://www.unten.co.jp/